国立公園制度について
初期の公園活動
日本では、1873(明治6)年に公園制度ができ、明治後半には、富士山や
日光を国立公園にという誓願が多数出された。
国立公園制度

昭和初期になると、各地で地元を国立公園
に誘致しようとする動きが広まる。
磐梯山周辺でも、滝を調査し名前を付けた
り、一般道路や登山道路を整備したりと、
様々な取り組みがあった。
1934(昭和9)年に国立公園法が制定され、
12ヶ所が指定されたが、磐梯山は選から
漏れた。当時の政治状況はまだ明治維新の
影響が残り、選定は西に多く東に少ない
結果となった。
磐梯山周辺は、朝日連峰と合併させられ、
1950(昭和25)年9月5日に17番目に指定を
受ける。
現在日本には国立公園は28ヶ所あり、その
中で火山が含まれていないものは、10ヶ所
だけである。
磐梯朝日国立公園の概要

「出羽三山・朝日」「飯豊」「磐梯吾妻」「猪苗
代湖」の4つの地域からなる面積約19万ha
の日本では3番目に大きな国立公園である。
山形、福島、新潟の3県にまたがり、飯豊
・朝日は原始性、磐梯吾妻及び猪苗代湖は
レクリェーション性、出羽三山は歴史性
に富む。
これからの国立公園について
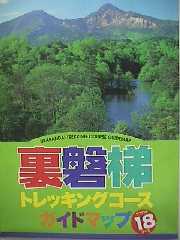
磐梯山周辺は、磐梯朝日国立公園の中で、福島県
ナンバーワンの自然の観光地として、年間350万人
余りの方が訪れている。
現在北塩原村では、トレッキングコースの整備を進
め、2001年には国際トレッキング大会を誘致する。
このすばらしい自然を利用した観光誘致活動はたい
へんよいことだ。
しかし、コースだけを整備しただけでは意味がない。
そのコースを村民が何度となく利用し、外から来る
人々を誰でもが、案内できるようにすることがたい
せつである。
また、この国立公園も未来に向けては問題がある。
それは、尾瀬沼などで言われているオーバーユースという利用人数が多す
ぎて、自然の生態系が崩れてしまうことである。
これ以外にも、生活排水や利用客のマナーの問題など様々存在している。
欧米の国立公園活動の先進地に学びながら、私たちが享受しているこのす
らしい自然を、後世の人々のために残すという意識を育てていかなければ
ならないと思う。